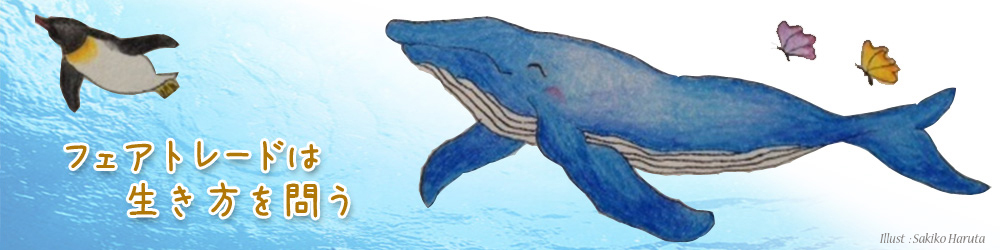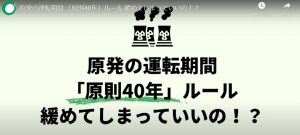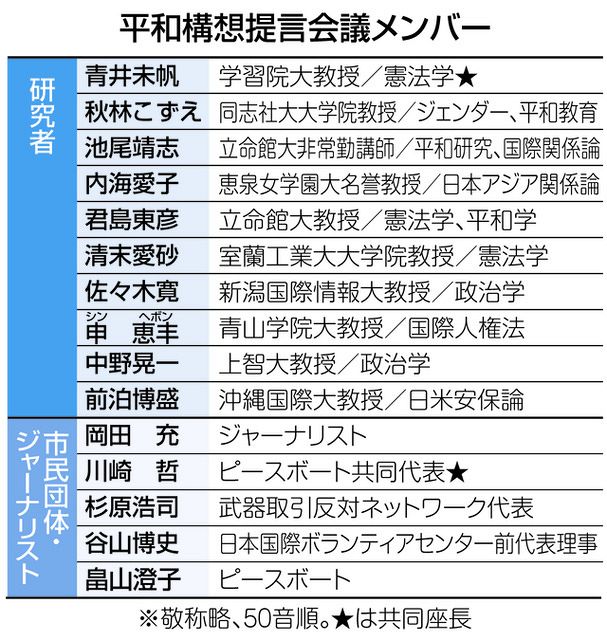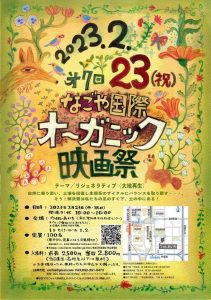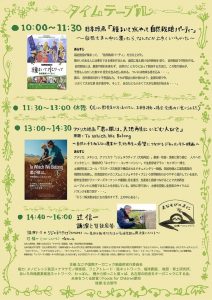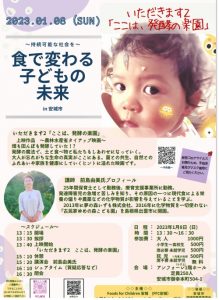12月15日 無料配信 「ムハマド・ユヌス氏と創る3つのゼロの世界」
貧困0・失業0・CO2排出0の新たな経済がありました。
パネリストは、斎藤幸平・中島岳志・末吉里花
以下が企画団体(なぜ?建築業界が?)
一般社団法人建設プロジェクト運営方式協議会,一般社団法人環境未来フォーラム,一般社団法人 PPP 推進支援機構」
なかなかよかったです。
グラミンバンクのことはおよそ知っていましたが、ユヌスさん自身から
その成り立ちを聞くことは貴重でした。
(始まりから数分は日本語音声切替に気が付かず途中からでしたが)
小さな野心、一人から(でもいいから)助けたい
同じ村にいながら高利貸と、お金がなく銀行からは借りれない貧しい人たちがいる。
現状を見て助けたいと思った。
人はみんなクリエーター、起業家と考えるべき
人は無限の想像力を持っている(村上和雄さんの遺伝子スイッチON につながる話だね)
生きる人を作れ
会社つとめして生きるロボットになった
人間であることを忘れている。お金が必要な奴隷
グラミンバンクは
チャリティではない、
人間の問題解決の会社(第3世界ショップの片岡勝と同じだね)
人に基づいたシステムづくりが必要。今のシステムを変えればいい。
人は利他の精神をもっている。
利益を得るなどの普通の幸せより、人を幸せにするするほうが
スーパーHappy
貧しい人には少しのお金でたりる
自分はお金があったから
「お金の欲しい人おいで」と呼び掛けた
一般の銀行とすべて反対
・貧しい人にお金を貸す
・すべての人にOK、拒絶しない
・担保はなし
・利益を求めない
・地域の問題解決をする など。。
・スーパーHappy
グラミンバンクは
現在アメリカで、35都市、10年たち、20万人以上利用
総額30億ドル ほとんどは移民の人、身元証明できない人
ユヌス教授はたぶ現在82歳くらい、いい顔だった。生で
話が聞けるのはやはりいい。
★幸平さん、初めに彼はマルクス主義ですと紹介した。
ユヌスさんは、マルクスは好きではないような発言。
でも私は、世にでていないマルクス文献の研究している
幸平さんとは思っていないのだろうと思う。
また、彼は、もう一つの0、それは成長を加えたいと言ったが
ユヌスさんはグローバルサウスの立場だから、Yesとは言わなかった。
★中島岳志さん、政治学者だけれど利他を研究しているそうだ。
自己責任 に違和感を感じる
それは、例えば自分は選んで日本にいて日本語をはなしているわけではない
すべて自分が選択しているわけではないから、
偶然性から別の人間であったかもしれないのだから。
九鬼周造の本の話もしてた。
難しい本らしい(チャットで言っていた)
日本語に「有難迷惑」という言葉がある。
利他は、受け入れてもらえてはじめて利他になる。
今の途上国(グローバルサウス)には
私たちが失ったもの、持っていないものがある。
他人を助ける、協力する、必要なものを作っていく、人間やりがいがあれば
幸せなんだ。
ユヌスさんの、事業が成功したのは
丸裸の人間性、根源的な信頼があたのであり
救いを求めている人に受け入れられた。
資本主義とは違う。
利他の精神を受け取って、渡してゆく。
私自身はそれをバングラデシュのスワローズや、メキシコのトセパン組合で
聞いてきました。
彼らはピープルツリーや、ウィンドァームから受けた利他の精神を
自分達より、さらに貧しい人たちへ手を差し伸べている。
★さて エシカルなんとやらの代表 末吉里花さん
隣にいる斎藤さんへ
エシカル商品を売ることはSDGsのまやかしといわれていることを言いつつ
(斎藤幸平著「ぼくは、ウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた」では
個人の努力次第で実現可能であるかのように吹聴する欺瞞こそが「エシカルな
暮らし」に私が最もイラつく理由という)
途上国に学んでいる、世界のことを知ることで
足元の暮らしから、地域から、そして世界へと変えていくというような
ま~私と同じような考えを述べていた。
フェアトレードは貿易のシステムを変えようという理念がある
今の貿易ではない、本来あるべき貿易。社会改革の運動の一つだと思う。
同時に貧困・環境・労働環境・ジェンダーと
本来、人として生きる姿を真ん中においていると思う。歴史もある
エシカルはやっぱりムードっぽい。
金持ちへのねたみ?「嘘っぽい」
だからイラつく人もいると幸平さんは言う。
今回の2人の男性、一人のエシカルをうたう女性のパネラーも共に
意識改革には必要だと思う。
男性性の経済学や哲学的なところから、理論で今のシステムを変えていく
ことを伝える方法もあり
女性性のような、身近なところから始まる。
まずは世界でおきていることを知って、想像して(わが身に置き換え)
どうしてそうなるのか考えて、行動する。
フェアトレードは、知るきっかけをつくることが出来、行動しやすい。
買う品がある。その品から
健康問題も含む環境問題など気づいていく機会がある。
この両性の行動の仕方、両輪は必要だと思う。
ただフェアトレードがあればエシカルはいらない。
フェアトレードを推進すれば、足元の暮らしを見つめなおすには
充分だと思う。紛らわしい。
アンケートの感想に、
末吉さんは以前ピープルツリーの
アンバサダーだったけれど、エシカルがはやってきたら
団体を作り代表になったので
全体の感想はとてもいいとしたうえで
「フェアトレードからエシカルに衣替えですか?」と
書き込みました。