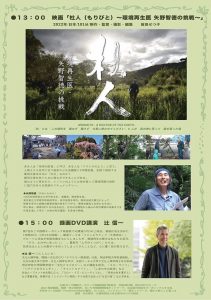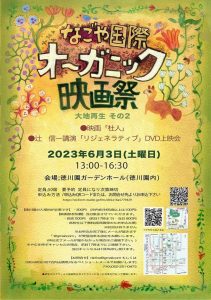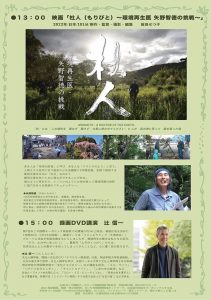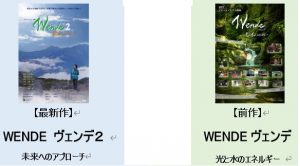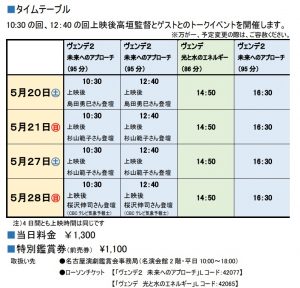原子力市民委員会より
この度、『今こそ知りたい エネルギー・温暖化政策Q&A(2023年版)――政府GXによる原発回帰は、国民負担が増すだけで、脱炭素にもエネルギー安定供給にもつながらない』を出版しました。下記のページからPDFでご覧いただけます。
http://www.ccnejapan.com/?p=13651
原発推進のGX関連法案については、ご存じのように、GX推進法案はすでに衆参本会議で可決され、GX脱炭素電源法案は4月27日に衆議院本会議で可決、5月10日に参議院で審議入りしている状況です。
しかし、原発推進に経済合理性はなく、電力の安定供給にも脱炭素にもつながらないことは明白であり、事故のリスクを高める運転延長をも含むこのGX関連法案の問題を多くの人々に伝え、廃案を求める声を強めていかなければなりません。
本Q&Aでは、原子力市民委員会のメンバーでもある明日香壽川さん(東北大学東北アジア研究センター・同大学院環境科学研究科教授)が、17の素朴な疑問に回答する形式で、日本政府のエネルギー・温暖化政策の数々の問題を解説しています。
ぜひお読みいただきたく思いますし、また多くの人々の目にとまるよう、本書を広く紹介いただけると幸いです
<目次>
──────────────────────────────
第1章 原発は安い?
■質問1 原発がないと電気代は高くなりませんか? 政府や電力会社は原発が再稼働すれば電力料金が下がると言っています。毎月の電気代に含まれる再エネ賦課金の額も大きく負担を感じます。
■質問2 世界的にも原発に回帰しているのではないでしょうか? EUもEUタクソノミーなどで原発推進を決めたのではありませんか?
■質問3 原発はCO2を出さないのですか? クリーンあるいはグリーンなのですか?
■質問4 原発新設、あるいはすでにある原発を使う方が温暖化対策に有効ではないですか?
■質問5 原発推進の英国は、原発のおかげでCO2排出量が減っているのではないですか? 一方、脱原発を表明しているドイツはエネルギー転換で失敗していて、電気をフランスから輸入しているのではありませんか?
■質問6 小型原子炉や核融合炉は有望な技術と聞きましたが、違うのでしょうか?
■質問7 原発は飛行機が突っ込んでも大丈夫だと聞きました。本当でしょうか? 福島第一原発のような、想定外の事故の危険性がある原発は他にもあるのでしょうか?
■質問8 原発があるから日本では再エネが普及しない、というのは本当でしょうか?
■質問9 なぜ米国、日本、フランス、イギリスなどは国策として原発を進めるのでしょうか? 将来核兵器を持てるようにするため、というのは本当でしょうか?
第2章 再エネは使えない? 省エネはもう無理?
■質問10 太陽光発電は、雨の日、雪の日、夜などは発電できないはずです。このように再エネは不安定なので、停電したり、電気を使うことをがまんしたりしなければならなくなるのですか? また、送電網の整備に余計なお金がかかるのではないですか? どうやって再エネ100%が可能になるのでしょうか?
■質問11 メガソーラーは自然破壊につながるのではないですか? メガソーラーがなければ、太陽光発電は増やせないのではありませんか?
■質問12 再エネの日本経済へのメリットは何ですか? 日本での太陽光発電で儲かるのは中国など海外の企業だけではないですか? 太陽光パネルの製造時に人権問題が絡んでいるのではありませんか?
■質問13 太陽光パネルは製造時に大量のエネルギーを使うのではないですか? 太陽光パネルの廃棄問題や電磁波の健康への影響があるのではないでしょうか?
■質問14 日本は省エネ先進国ではないのですか?
第3章 電気自動車は問題あり?
■質問15 電気自動車で電力需要が増大するのではないですか?
■質問16 ライフサイクルで考えると電気自動車はCO2排出削減につながらないのではありませんか?
第4章 政府GX基本方針は問題だらけ?
■質問17 GX基本方針における投資分野・内容、GX経済移行債、成長志向型カーボンプライシング、GX推進機構の問題点とは何ですか?
──────────────────────────────
なお、冊子版の購入もいただけますが、現時点での発送は5月25日頃を予定しています。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
http://www.ccnejapan.com/?p=13651
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
——————————————-
原子力市民委員会 事務局
〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4-15 新井ビル3階
(高木仁三郎市民科学基金内)
TEL/FAX: 03-3358-7064
URL : http://www.ccnejapan.com/
e-mail : email@ccnejapan.com
Twitter: https://twitter.com/ccnejp
Facebook: https://www.facebook.com/ccnejapan
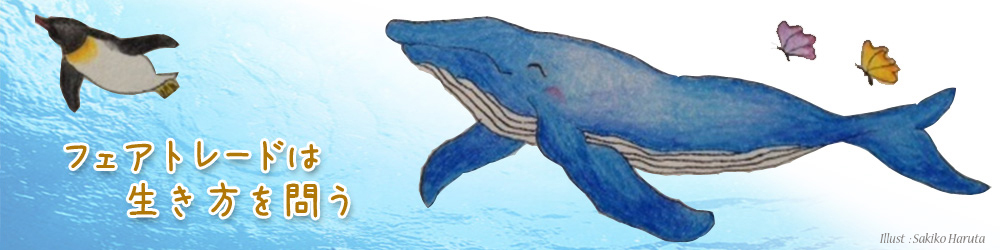

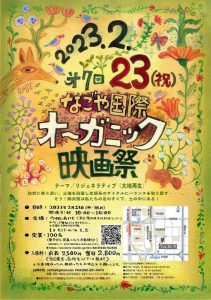
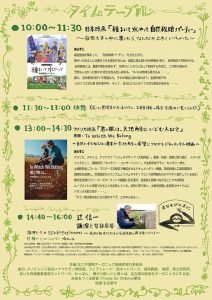

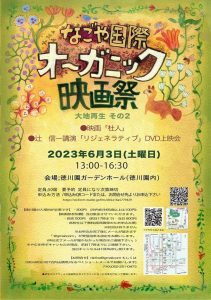 http://huzu.jp/goods/7853/
http://huzu.jp/goods/7853/